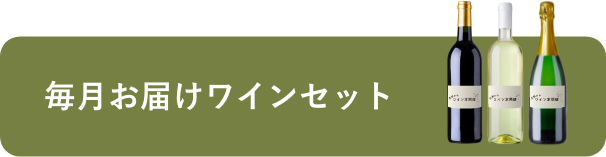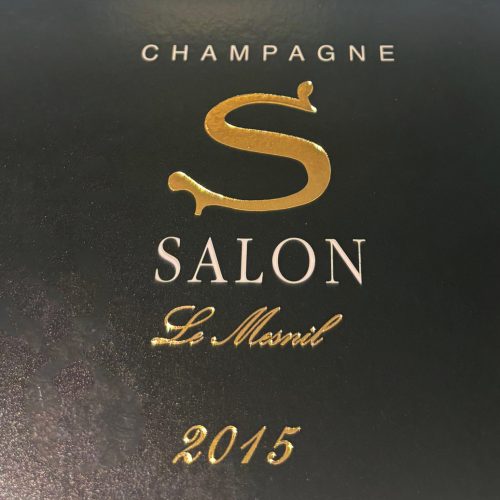こんにちは!業務部の中谷です。去る2月、NZに研修に行ってまいりました!
今回はレポートの第三弾として「リッポン・ヴィンヤード」の訪問時の様子をご紹介いたします。
※本訪問では、サトウ・ワインズの佐藤氏のご厚意により、同行と通訳のサポートをしていただきました。大変お世話になりました。本当にありがとうございます!


■リッポン・ヴィンヤードの原点
リッポン・ヴィンヤードの物語は、ワインの歴史にとどまらず、ニュージーランドという国の成り立ちそのものに深く結びついています。
数千万年前、まだ哺乳類のほとんど存在しなかったこの大地には、鳥たちが独自の進化を遂げる豊かな自然環境がありました。13世紀頃になって、ポリネシアから渡来したマオリ族によってこの土地に人の営みが始まります。1840年にはイギリスとマオリ族との間に「ワイタンギ条約」が結ばれ、ニュージーランドは植民地国家として新たな時代へと歩み始めました。そのなかで、オタゴのゴールドラッシュが、南島の発展を一気に加速させます。特にダニーデンの街はその中心となり、当時ニュージーランドで最も栄えた都市となります。
成功を収めた人々の中には、スコットランド出身の実業家ウィリアム・リッポン(William Rippon)の姿もありました。1858年、彼の娘であるエマ・リッポン(Emma Rippon)は、相続の中でオークションで家族の土地を売却。その資金をもとに、現在のワナカ湖畔にある土地に農場を拓き、これがリッポン・ヴィンヤードの原点となります。以来、この土地はリッポン家によって守り続けられ、1912年にワイナリーとして手探りで開業。現在は4代目にあたるニック・ミルズ氏(Nick Mills)が当主としてワイナリーを牽引しています。
ブルゴーニュでワイン造りを学んだニック氏は、リッポンの地を単なるブドウ栽培地としてではなく、
「土地の記憶を映し出す存在」として捉え、自然と調和するビオディナミ農法を実践しています。


■ ブドウ造りのアプローチ フィロキセラ対策
セントラル・オタゴでも2000年代に入り、徐々にフィロキセラの侵入が確認されるようになりました。世界中のブドウ畑を壊滅させたこの害虫に対し、多くの生産者は台木を用いた接ぎ木栽培へと移行する中、リッポン・ヴィンヤードは今も一部では「自根のブドウ樹」を守り続けています。
この選択は、簡単なものではありません。自根のブドウはフィロキセラに対して脆弱であり、そのリスクを背負うには相応の覚悟と準備が必要です。リッポンではこの「脆さ」を補い、むしろ強さに変えるための農法と哲学を実践しています。
1. 土壌の選定と理解
リッポンの畑は片麻岩由来のミネラル豊富な土壌に覆われており、排水性と根の深さを活かした栽培が可能です。この土壌構造がフィロキセラの繁殖に適しづらいという特性を持っています。
2. ビオディナミ農法の実践
自然のリズム(月の満ち欠けや天体の動き)に合わせて農作業を行い、土地の生命力を最大限に引き出すビオディナミ農法を採用。自家製の有機肥料を使用しています。これにより、ブドウ樹そのものの免疫力や回復力が高まり、害虫にも強くなります。
3. 自根へのこだわり
「土地の声を最もピュアに反映するのは自根のブドウ樹」と考えるリッポンでは、接ぎ木による介在を極力避け、テロワールの純粋な表現を追求。これは品質と哲学の両面で、彼らにとって譲れない信念だそうです。
4. モニタリングと生態系管理
圃場のモニタリングを定期的に実施し、害虫の兆候をいち早く察知。農薬に頼るのではなく、畑全体のバランスを整えることで病害虫の発生を抑制するというアプローチをとっています。
■畑に関して

ワナカ湖とロブ・ロイ氷河の狭間に息づく場所であるリッポン・ヴィンヤードを訪れて、まずその雄大な風景に圧倒されました。
ワナカ湖の湖畔に広がる畑と、遠くに望むロブ・ロイ氷河から冷たい風が吹き下ろし、昼夜の寒暖差を生み出すそうです。
全体的に北向きの斜面は日照に恵まれ、ブドウの成熟をしっかりと支えてるとの事。
この土地の土壌は、氷河によって削られ運ばれたシストや粘板岩、砂利から構成されており、非常に水はけが良い自慢と土地と仰ってました。畑の規模は全体で14haでここ一帯の雨量は僅か600mでかなり少ない地域。山から流れる水を大抵のところは貯水湖で貯めておくそうで、リッポンも勿論もっておられました。
畑全体は細かく区画分けされ、それぞれの区画が固有の特徴を持っています。
中でも代表的な畑がふたつあります。
•エマズ・ブロック(Emma’s Block)0.8ha
鉄分を含む赤みがかった土壌で、ピノ・ノワールに品格と繊細さを与える区画。やや内向的だが、時間とともに複雑さが花開くワインが生まれる。代々、最も愛着のある区画であり、ピノ・ノワールとしての表現ではなく、『エマズ・ブロック』を表現し続けているそうです。
•ティンカーズ・フィールド(Tinker‘s Field)2.5haで内1.7haがピノ・ノワール
リッポン最古のピノ・ノワール区画で、自根の古木が多く残り、セントラル・オタゴで一番古い樹も存在している。構造がしっかりとし、力強くストレートなエネルギーを備えたワインを生み出すそう。リッポンのフラッグシップともいえる区画です。
そのほかにも、レベッカズ・ブロック(Rebecca’s Block)やニックス・ブロック(Nick’s Block)ジェームズ・ブロック(James’s Block)など家族の名前を冠した区画が点在し、それぞれに異なるピノ・ノワールの表情が育まれているそうです。
■ 醸造に関して


1. 醸造施設もともとヤギ小屋の跡地を改装して作られた醸造施設だそうです。このユニークな背景が、自然志向の哲学を象徴している気もしました。ヤギ小屋の古い構造が、温もりと独特の雰囲気を醸し出し、醸造過程にもその影響が色濃く表れています。
2. ビオディナミのアプローチ
ビオカレンダーを参考に地球と自然のリズムに従いながら必要な工程を行い、醸造過程でも、自然酵母を使用して発酵を進め、酸化防止剤を極力抑えた形で醸造をされます。
3. 小ロット醸造と手作業
こだわりのひとつとして醸造は基本的に各区画ごとに小ロットで行われます。これにより、テロワールの個性が最大限に活かして、マチュアなどのバランスを考えます。また、樽にニックネームをつけてます。人の名前や、味わいのイメージ、日本語などもありました。
4. 熟成と瓶詰め
フレンチオーク樽での熟成が行われ、ニックさんはアメリカンオーク樽より深みと複雑さを増すと言います。その後、熟成が進んだ段階で瓶詰めされ、長期間熟成を続けるものもあります。こうした過程を経て、リッポンのワインはただの飲み物にとどまらず、その土地と歴史を感じさせる芸術作品として完成します。


■ テイスティング

■赤ワイン
★マチュア ピノ・ノワール 2021
透明感のあるルビー色。レッドチェリーやラズベリーに、ほのかなスモークとドライハーブ。タンニンは細かく、酸と調和しながら繊細なストラクチャーを形成。ヴィンヤード全体の調和を表現するスタンダード的存在。リッポンの全体像を語る、基礎となるピノ・ノワール。
★エマズ・ブロック 2021
華やかというより、静かな佇まい。熟した赤果実、ドライローズ、鉄分を思わせるミネラルが感じられ、舌の上でふわりと広がる。優しさの中に緻密さがある、リッポンの美意識がよく表れた1本。まるでシャンボール・ミュジニーのような繊細な赤ワイン。
★ティンカーズ・フィールド 2021
黒系果実とスパイスのニュアンスが印象的。より土壌の表情を感じる風味構成で、しっかりとしたテクスチャーと奥行きがある。自根ゆえの直線的なエネルギーがあり、時間とともに複雑性がじわりと広がる。力強さとストラクチャーを感じられ、芯のあるヴォーヌ・ロマネのニュアンスのあるワイン。
★マチュア ピノ・ノワール 2010
ドライチェリーや紅茶葉、湿った土など、熟成由来の複雑な香り。アタックは柔らかく、タンニンは完全に溶け込んでいる。構造は崩れず、しっかりとした背骨が残る。
■白ワイン
☆ソーヴィニョンブラン 2023
ハーブや白い柑橘、カリンのような果実香が穏やかに立ち上がる。アタックは軽やかで、ほのかにミネラル感のある伸びやかな酸が全体をまとめている。爽やかで伸びやかな余韻が心地よい。
☆リースリング 2023
グリーンアップル、ライム、白い花。アロマはやや控えめながら、口中では緊張感のある酸が印象的。しっかりとした骨格と、塩味を帯びたミネラリティが余韻を引き締め、熟成の可能性も感じさせる。中辛口の華やかな白ワインです。
☆ゲヴェルツトラミネール 2023
バラやライチといった典型的なアロマはあるものの、過剰な甘さはなく、ドライで洗練された印象。わずかなタンニンとスパイス感が骨格を与え、冷涼地の個性がよく表れている。食中にも寄り添うスタイル。

ちなみに、すべてのワインで採用しているのはディアムの『オリジン』コルク使用しているそうです。この『オリジン』は、天然コルクの風合いと機能性を備えながらも、ワインへの影響を極限まで排除した設計が特徴だそうです。
使用されている接着剤も合成素材ではなく、植物由来のナチュラルボンドが採用されており、環境への配慮と品質安定性の両立が図られていて、サスティナブルであると嬉しそうにお話しされていました。
■まとめ
リッポンへの訪問も、大変貴重な時間でした。
セントラル・オタゴにおけるワイン造りの歴史と可能性を体現する存在であり、土地の成り立ちから栽培、醸造、ボトリングに至るまで、一貫して「自然との共生」という姿勢が貫かれており、どの要素を取っても、一過性の流行や外的要因に流されることなく、リッポンは独自の歩みを続けているのを肌で感じました。また、今回訪問を通して、造り手の哲学がブレることなく次の世代へと自然に受け継がれているという持続可能なポリシーに感銘を受けました。
終始ニュージーランドの大地とワイナリーについて熱く語って下さったニック氏。
ニュージーランドとリッポンの情熱の結晶のようなワインを日本の皆様にも是非味わっていただきたいです!
▶2025年5月17日「ニュージーランドワインのセミナー」開催します!🍷
#ワイングロッサリー #京都ワインショップ #京都 #ワイン #kyotowine #winegrocery
#ニュージーランドワイン #リッポン #Rippon